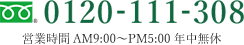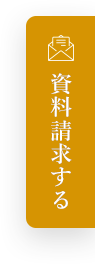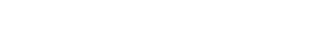日本の土葬事情

日本に住むイスラム教徒は34万人にも達するといわれ、移民人口の増加とともに「墓不足」が深刻な問題となっており、各地で「闇土葬」ともいえる違法埋葬が発生している、といったことを、昨今ニュースで見聞きすることが増えました。
昔は日本でも土葬だった、というのは周知の事実かと思います。
ではいつから日本は土葬を行なわなくなったのでしょうか。
実は日本には土葬を禁止する法律はありません。
ですが、1948年の「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」制定後に、都市部で土葬用墓地の不足や衛生上の問題が顕在化し、多くの自治体が条例で火葬を義務付けたり、土葬を制限したりするようになったとされています。
つまり、国の法律として土葬は禁止されていないが、各自治体レベルの条例により、実質的に禁止または制限されているというのが現実です。
ニュースを読むと、土葬可能な霊園に許可なく埋葬していた、と読み取れる部分がありました。
一部地域では現在でも土葬の許可を出しています。
その土葬を実施できる地域であっても、自由に埋葬が行なえるわけではありません。「埋葬」は法律上、火葬と同様に行政手続き、墓地管理者からの許可が必要になります。
日本人でさえ、亡くなったあとの手続きは不慣れなのでどうしていいかわからないことが多いものです。
ましてそれが移民となるとさらにハードルが上がるのは目に見えています。
移住者増加にあたって、行政手続きなどの周知が課題であることは間違いなさそうです。